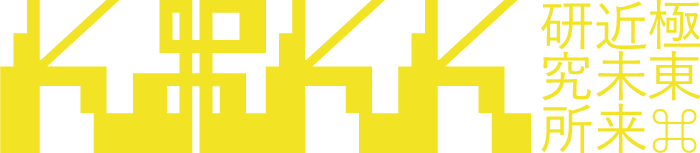若い頃から、建築物と植物の関係に惹かれている。簡単にいうと、「建物に囲まれた静かな中庭にある鬱蒼とした緑」や、「緑に覆い尽くされそうな建物」だ。特に自分が前者に目覚めたのは、前回の投稿で触れた、中学校の中庭を深夜に見た時だ。
ロの字に校舎に囲まれた中庭では、真っ暗な中で木々が強烈なスポットライトに照らされ、池に注ぐ水の音だけが静かに聞こえていた。その時は単に神秘的で格好いいという感覚だけがあった。

「建築物と植物の関係」をはっきり意識しだしたのは、映画「ロビンソンの庭」(1987)を観たのがきっかけではないかと思う。緑の生い茂る廃墟に迷い込んだ主人公が、都会の喧騒から隔離されたその空間に奇妙な懐かしさを抱き移り住むというストーリーなのだが、ストーリーよりもその舞台になっている広大な緑地と、校舎のような建物の関係にしばらく虜になった。
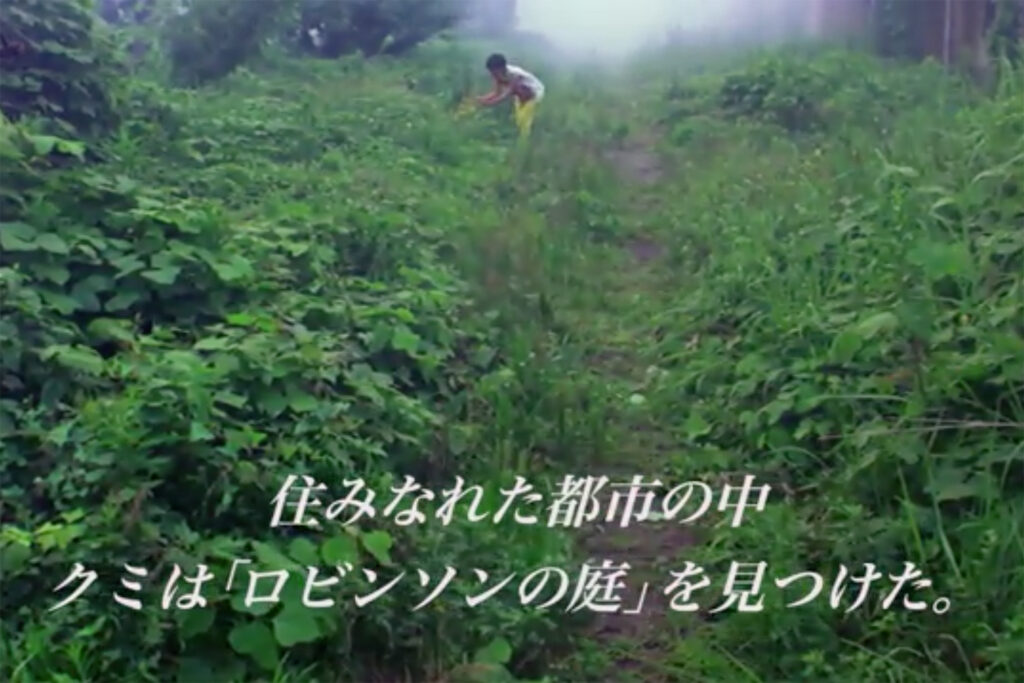


80年代の東京にはまだ多くの廃墟のような場所があり、よくロケ地として使われていたそうだ。「ロビンソンの庭」のロケ地は旧 蚕糸試験場(現 蚕糸の森公園)だとか、初台の東京工業試験所の跡地だとか言われているが、ロケ地はカットによって使い分けられるだろうし、情報が少なく結局よく分からない。ただ、東京工業試験所跡地は「ドレミファ娘の血は騒ぐ」のロケ地としても使われており、好きな作品の思わぬ共通点を知り驚いた。
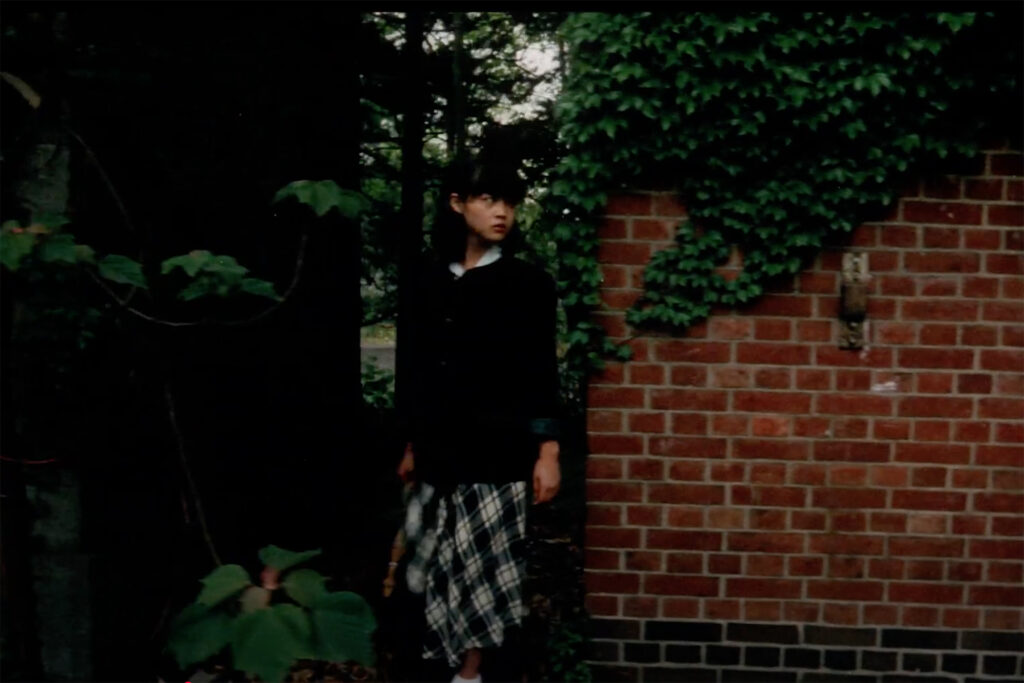
街を歩いていると時々、建物の間で過成長気味に繁茂した植生を見かける。人による管理から逃れた緑は不健全な存在として位置づけられがちだが、街を飲み込むその姿に退廃的な美しさを感じるのは自分だけだろうか。不健全なのに美しい—— 今回はその違和感を整理する試みからスタートし、実例を挙げてみた。
公園機能と楽園
最近話題の公園を挙げるとすれば、例えば……JR大阪駅北側の再開発エリアに誕生した「うめきた公園」。グラングリーン大阪の南北に広がるその公園のコンセプトは「誰もが思い思いに過ごすことのできる開放的な公園」であり、実際に誰もが(もちろん自分にとっても)心地良いと感じるスポットになっている。ただ……
「自然と調和した」「自然の中でリラックス」「防災機能」……等々、うめきた公園は公共性の高い施設として存在はするが、自分が公園に求める癒しのようなものがあるわけではない。
自分が公園に求める機能を簡単に言うならば、そこだけ鬱蒼と木々が茂る「鎮守の森」に近い存在ではないかと思う。神社を囲むように存在するその森は、地域を守る神が宿る場所とされるとともに、人々は鎮守の森の存在を通して、癒しや安らぎを感じてきた。その神聖な場所に一歩踏み入れると、森の木々や自然のエネルギーが、訪れる人々に安らぎや活力を与えてくれると考えられている。

現代の都市には綺麗にデザインされた植栽(緑地、公園)があるだけで、鎮守の森から得られるような安らぎは求めることができない。別に、森ではなくても、例えば坪庭でもいい。求めているのは規模に関係なく「楽園」である。
鬱蒼とした楽園の定義
「楽園」というと一般的には理想郷、平和や幸福を連想させる聖なる場所をイメージさせるが、ここでは「公園」に対して「建築物と植物の関係」を意識させる鬱蒼とした緑や、緑に覆い尽くされそうな建物のある場所について語りたいので、便宜上「鬱蒼とした楽園」と呼びたい。そこで、まずは「鬱蒼とした楽園」の定義づけを行いたい。
なお、タイトルで「楽園と廃墟美の境界線」という表現を用いているが、「鬱蒼とした楽園」と廃墟美は相反するものではなく、「鬱蒼とした楽園」が廃墟美を併せ持つ関係にあることをあらかじめ断っておきたい。もちろん純粋な廃墟にも廃墟美があることは多いが、廃墟は楽園ではない。例えば「天空の城ラピュタ」は自然と人工物が調和した美しい場所として描かれてはいるが、本来は大きな括りでは廃墟であり、楽園ではない。
「鬱蒼とした楽園」は概ね次の項目を満たすものである。
周囲から隔離されていること
騒がしい街なかや平凡な日常生活の流れの中にあっても、ロの字型の建築物に囲まれることで周囲から切り離され、独立した自由な時間が流れる空間を形成している。もしくは、周囲の騒音が届かないほど深い森に包まれた中央に緑に覆い尽くされそうな建物がある。適度な包まれ感が心地よく感じる。

人の気配がないこと
自分(や自分と一緒に行動している人たち)以外の、いわゆる他人の気配がなく、静かである。耳を澄ますと木々の葉が風に揺れる音が聞こえ、月に照らされた中庭の池では水の注がれる音が聞こえている。何かの気配を感じて振り返ると、建物を緑が覆っている。自然の生命の気配を感じる。

廃墟ではないこと
人の気配がないといっても、営業時間の過ぎた公園や深夜の学校の中庭など、時間帯により誰もいなくなったり、建物や森に遮られて周囲から隔離されているだけである。人の気配が残っていること、感じられることは重要である。

草木が盛んに生い茂っていること
一般的な公園には管理が行き届いた植栽が綺麗にレイアウトされるが、鬱蒼とした楽園を構成する重要な要素は「鬱蒼とした緑や、緑に覆い尽くされそうな建物」である。植物はひとたび人による手入れを逃れると一気に、または時間をかけてじわじわと着実に繁殖する。それが管理された公園の植栽や畑ではなく建築物を覆い尽くそうとする状態である時、人はその成長エネルギーに一種の恐怖を感じる。ただ、植物の多様な形態や豊な色彩には絶対的な美しさがあり、恐怖と美しさの相反する要素が同居した時、廃墟的な美しさとしてアウトプットされる。

都心部にあること
ロの字型の建築物で周囲から切り離された空間や、緑に覆い尽くされそうな建物であっても、それが人里離れた緑豊かな土地にある場合、周囲とのギャップが生まれず楽園にはならない。都市の喧騒から切り離されることではじめて、その場所が特別な楽園となる。
できれば水があること
触れたら気持ちが良いというイメージによるものか、光によるきらめきか。アルハンブラ宮殿やロビンソンの庭でも水は、なくてはならない重要な要素となっている。ただそこに豊富にあるだけで良く、噴水や川のように勢いよく流れている必要はないが、静かな中に微かに水の音がするととても良い。

鬱蒼とした楽園を街なかに探す
漠然と自分が惹かれてきた「鬱蒼とした楽園」について、今回の投稿である程度整理ができた。が、若い頃の経験がピーク・エンドの法則により偏ったイメージとして、美しく記憶されているところもあるだろう。そこで、「鬱蒼とした楽園」が具体的にどこにあるのか身の回りで探してみた。
実際には難しい課題となったが、それに近い場所を規模が大きなものから紹介する。
作られた緑地/公園
もともと公園は楽園に近い。下の千里万博記念公園(自然文化園)には開園時間という制約が設けられ、また周りを高い柵で囲われている。航空写真で引いて見ると都市の中にぽっかりと緑地があり、隔離されているように見える。
1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)の跡地を整備した公園で、開園は1972年。長い年月により樹木は大きく育ち、いい意味で鬱蒼と茂っている。

河川敷/ワンド
画像は淀川の城北ワンド。一般的に河川敷の多くには緑地があるが、大規模なワンドが設けられたここでは水面の間に樹木が入り組み、独特な雰囲気を形作っている。夜や朝方に釣りでもしにに来ると、街なかなのに静けさを感じることができる。ジャングルのようなワンドと、向こうに望む梅田のビル群との対比が面白い。

病院の中庭
写真は、旧日本赤十字社大阪支部病院(解体され現存しない)。1980年代に撮影したモノクロ写真からスキャンしてみた。鉄筋コンクリート造5階建の病棟自体も建築好きから愛された建物だったが、その独特な病棟に囲まれた中庭がまた「鬱蒼とした楽園」そのものだった。
病院という施設そのものが世間から隔離されているイメージもあるが、一つの世界観ができていたここの中庭は、個人的に魅力的な被写体であった。


植物園/温室
植物園に行くと、ワクワクする。見たことのないような植物がたくさんあって、写真でも撮ってみようかという気になる。そしてもう一つの楽しみが温室。暑い寒いに弱いのだけど、いつ行っても一定の温度で気持ちがいい。ガラスという好きな素材で覆われていて、緑がたくさん。冬の暗く曇った日の午後がいいかもしれない。

前庭/裏庭
街を歩いていて緑の勢いに突然目を奪われることが稀にあるとしても、ここまで立派なところにはなかなか出会えない。鬱蒼とした楽園を構成する鬱蒼とした緑は、荒れ放題な緑ではない。

一見荒れ放題に見えても、実は一定の管理がされていることはある。そのギリギリの状態が、最も美しいと思う時がある。

上階に作られた森
ビルの上にある緑には無条件に惹きつけられる。屋上庭園、屋上緑化も良いが開放的な雰囲気のところが多いので、こういった部分的なテラスにある緑が好きだ。下の写真は、西梅田にある飲食店ビルの3階部分。隣のビルが取り壊されて顕になったが、元々は採光を目的とした坪庭的なものだったのだろう。食べログに投稿された写真を見るとエキゾチックなテラスにも見えるが、外から見るとかなり勢いよく伸びている。

プライベートな森
リビングの延長線上に設けた自宅のバルコニーも、目標は鬱蒼とした楽園だ。園芸の趣味は無いので一度植えたら水やり以外の手入れをしないし、格好いい植物を次々と買ってくることもないので一向に楽園には近づかないが、夜に水槽のメダカを見ながらボーッとするのには良い。

メダカたちのいる水槽
アクアリウムが目的ではないのだが、メダカを飼っている水槽にも楽園的な要素を大いに感じる。ガラスで閉ざされた空間、中は水で満たされ静かで、植物の勢いが増す季節はまるで森のよう。アクアリウムの世界の人たちは綺麗な景色を作り込むが、自分の水槽はいい加減なところがどこか廃墟っぽく、自分好みでもある。

実際はメダカたちが戯れあって騒がしいのだけど、日光がキラキラと反射する水面は美しく、いつまでも見ていられる。

下は、メダカの卵を隔離させたガラスの食器(稚魚は成魚と離す必要がある)。水と光と緑があれば、小さなガラス容器でも立派な楽園になる。そう、万華鏡やもっと言えばビー玉の中にも楽園を見出すことはできるだろう。もっと見つけてみよう。

今回は、建築物と植物の関係の中から、「建物に囲まれた静かな中庭にある鬱蒼とした緑」について好き勝手に触れてみた。いつか、「緑に覆い尽くされそうな建物」についても触れてみたいと考えている。これまでそういった物件を収集してきたわけでは無いので、当分は歩く時に注意したり、意識して普段とは違う道を通るなどしてみよう。